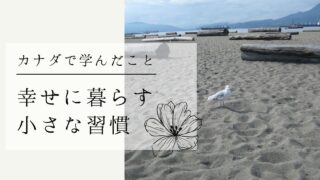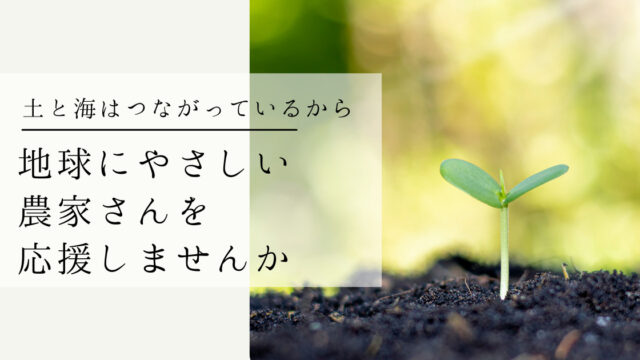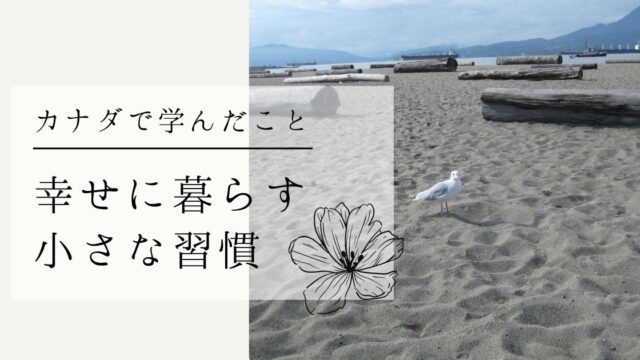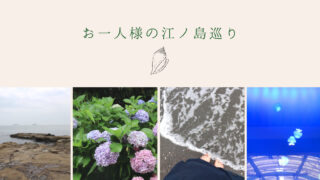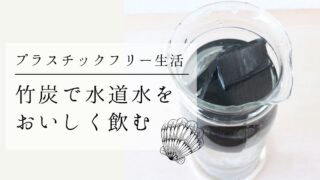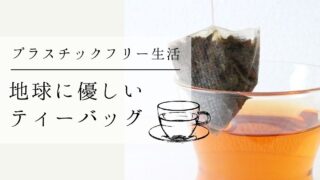昔の暮らしは不便だったけど、その分地球に優しい暮らしだったなあと思うことがあります。
例えば、電子レンジ
私が子供の頃は、電子レンジなんてなくて、お弁当は冷たいまま食べるのが当たり前でした。
電子レンジが壊れた時、別になくてもいいよねと思い電子レンジなしで生活していたことがあります。多少手間はかかりますけど、鍋で温めればいいので特に問題なしでした。
今のように便利ではないけど地球に優しい暮らしがもっと身近にあった昭和の時代
そこから学べることは多いのではないでしょうか。
昭和に学ぶエコ生活
ということで、今日紹介したい本はこちらです。
この本では高度経済成長期前(昭和30年より前)のライフスタイルから地球に優しい暮らしのヒントが得られます。
私自身も生まれる前の時代ですから、初めて知ることや、思わずへえ〜と思うような暮らしのアイデアがたくさん紹介されていました。
その中でも特に簡単そうなことから日々の暮らしに取り入れてみることにしました。
暮らしにヘチマを取り入れる
まず最初は身近に栽培できる植物を日常の道具として暮らしに取り入れるというもの
具体的にはヘチマ
昭和の時代、ヘチマは小学校の理科の授業の一環で育てられることもあったそう。
夏には日除けとして庭で育てている家庭も多かったのだそうです。
そんな身近にあったヘチマの身を使ってたわしにする方法が紹介されていました。
残念ながら我が家の場合は賃貸住宅で、庭でヘチマを育てることはできないので、
いつの日かヘチマを育てる庭のあるお家で暮らすのが夢だったりします。
自分で育てられなくとも、ヘチマのたわしは購入することができます。
他にも、ヘチマには保湿効果があり、化粧水の原料としても使われるそうです。
調べてみるとヘチマを使った化粧水は現代でもさまざまなものがありました。
水はいったん溜めて使う
現代の暮らしでは蛇口をひねれば水が流れるのはごく当たり前のことで
その分、自分がどのくらいの水を使ったのか分かりにくいです。
例えば、食器洗いの時、無意識に水を出しっぱなしにしてしまうことがよくあります。
試しにおけに水を流してみるとあっという間にいっぱいになりました。
おけに水を溜めて食器洗いすることで、水の節約になり、水道代の節約にもなります。
水をいったん溜めることで水の量を目で見ることができるので、意識的に水を大切に使おうという気持ちにもなりますよね。
これは洗濯の時も同じで、洗濯機のスイッチひとつで水は勝手に流れてくるので、どのくらいの水が使われているのか気づきにくいんです。
ほんの少しの洗濯物を洗うのならわざわざ洗濯機に入れて洗うのではなく、おけに水を溜めて手洗いするというのもいいかもしれません。
ほうきと雑巾で心を込めて掃除する
またまた我が家の話ですが、長年使っていた掃除機が故障した際にも、掃除機なくてもいいかもと思いました。
今はお掃除にはこちらのほうきと手縫いの雑巾を使っています。
ほうきで全然問題ありません。十分でした。
何よりもメリットと感じるのは、何時でも掃除できること。
掃除機は夜中に使うことはできませんし、
集合住宅なので早朝や、休日の午前中も気を遣います。
その点、ほうきならいつでも気兼ねがく掃除できます。
気づいた時にさっと掃けるので、こまめに掃除するようになり、掃除機を使っていた頃より部屋の中が綺麗になった気がします。
ほうきと雑巾を使って、腰をかがめ、床に近づいて、手を使って掃除していると
気分もスッキリします。
電気も使わず、自然素材で、地球に優しいお掃除方法です。
まとめ
昭和に学ぶエコ生活を読んで、地球に優しい暮らしの知恵を紹介しました。
この本の中では、他にもさまざまな暮らしの知恵が紹介されています。
気軽に取り入れられるものが多いですので、興味がありましたら読んでみてください。
▽海と糸の編み物記事はこちらから
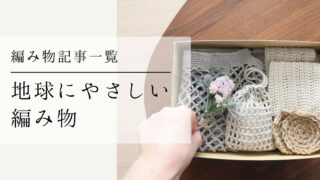
▽プラスチックフリー生活、今日からできること

▽地球に優しい農家さんを応援しています。
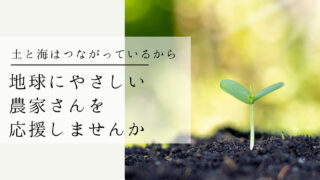
▽カナダで学んだ幸せに暮らす小さなコツ